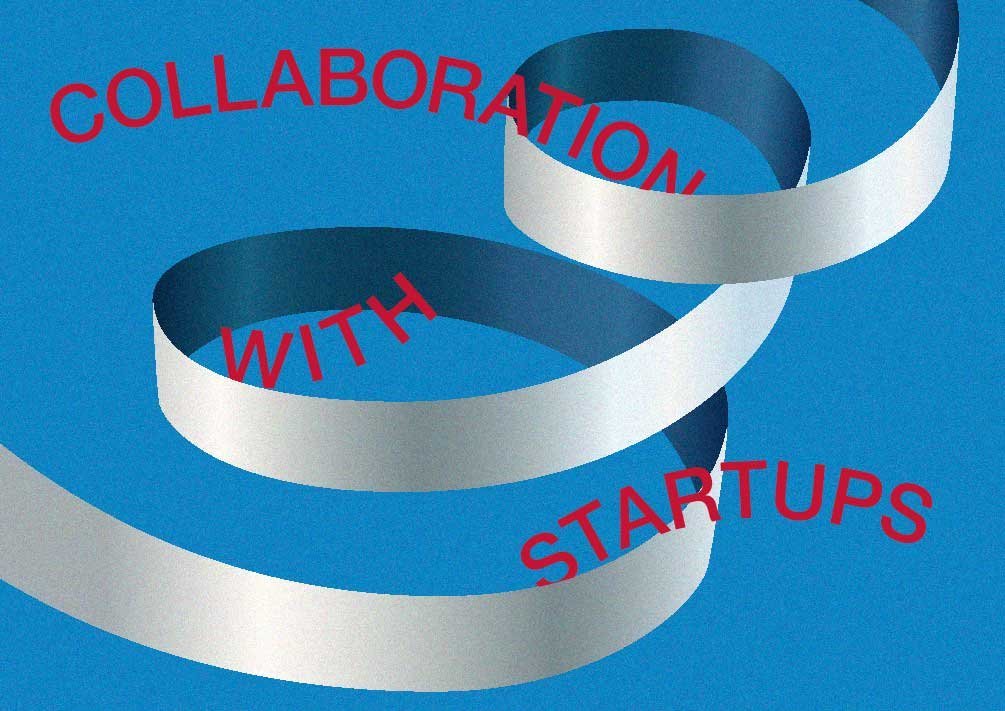Index
「女性が生涯スポーツを楽しめる世界にしたい」そう語るのはパナソニック株式会社 アプライアンス社の池田雅子。自身も幼少期から水泳競技の世界に入り、シンクロナイズドスイミング(現アーティスティックスイミング)では福岡県代表として国民体育大会(国体)に参加した経験を持っています。そんな池田が危機感を持ち、解決の糸口を探しているのが「女性の生理」に関する課題です。
シンクロきっかけにパナソニック入社、家庭と仕事を柔軟に両立

ビジネスコンテストプログラム「Boot Camp」の様子
池田「私が松下電器産業株式会社(現パナソニック株式会社)に入社したのは、シンクロで使われる音楽がきっかけで、音楽編集や水中スピーカーなどの音響機器に関心を持ったからです。大学時代に選手としては引退しましたが、コーチと審判員の資格を取得して、シンクロには継続的に関わっていました。入社後は研究部門に配属され、音響関連の研究に従事。結婚・出産、シリコンバレーへの移住、帰国を経て、現在はアプライアンス社のGame Changer Catapult(以下、GCカタパルト)の中のヘルスサポートプロジェクトで、人々の幸せを支え、生活を豊かにする新規事業の創出に向けて活動。並行して、GCカタパルトのビジネスコンテストをサポートしています」
GCカタパルトのビジネスコンテストでは「メンター」として参加チームのメンタリングやアシストを行う池田。助言を与えるというよりも、チームに寄り添い1人のユーザーとして接する姿勢を大切にしていると話します。
池田「入社当時からパナソニックでの勤務環境はとても整っていました。在宅勤務の利用や産休・育休の取得はスムーズで、上司とのコミュニケーションも取れていたので、育休からの復職時にも不安はありませんでした。それら勤怠面は研究や技術職という部署柄もあったと思いますが、女性としてのライフステージが変化するたびに、柔軟にキャリアプランを変更して、無理なく仕事に取り組むことができています」
「いい競技成績を残すため」と軽視されがちな女性アスリートの生理への向き合い方
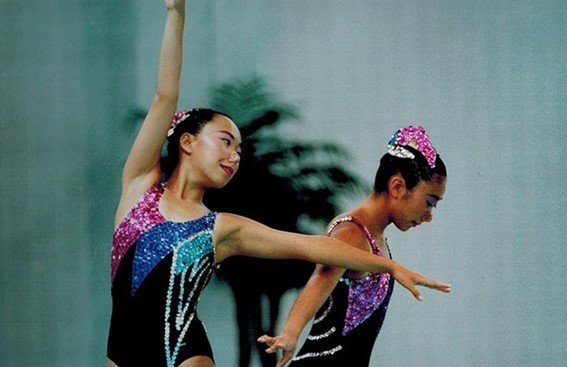
高校時代の大会でのひとコマ
パナソニックでいくつかの部署を経験し、現在はメンターの活動も続けながら新規事業のアイデアを探る池田。課題を意識したきっかけは、シンクロのコーチ研修でした。
「現役時代は私も生理は『みんな我慢しているのだろう』と思い込んでいました。しかしコーチの資格更新研修を受けた際、生理が止まることによる健康への影響を学ぶことで、女性アスリートの現状を理解しました。そして調査や専門家へのヒアリングを重ねるほど、いかに難しい課題であるか実感しました。例えばアスリートはいい競技成績を残すため、ハードなトレーニングや減量を行いますが、無理なダイエットなどを続ければ栄養不足となり、生理が止まってしまいます。そうなると骨密度にも影響し骨折しやすくなる、身長が伸びにくくなるといったリスクも大きくなりますし、将来的には骨粗しょう症の発症につながる危険性もあります」
池田が語るように、正しい知識を学べる機会が少ないのが現状です。これは当事者だけではなく、周囲の環境の問題でもあり、大きな課題になっています。
池田「生理が止まってしまう原因は、単なる栄養不足以外にもさまざまな病気が要因である可能性もあります。デリケートな話題ですのでコミュニケーションが難しいとは思いますが、当事者も周囲の大人も、もっと真剣に考える必要がありますね」
また、池田は現状を伝えるための情報発信が重要だと続けます。
池田「最近、女性アスリートの生理について、アスリートからの発信も増えてきています。パナソニックが若者への実験の場として提供している100BANCH(ヒャクバンチ)でも、女性アスリート100人のリアルな声を届けるというプロジェクトを行なっていて、私も少しだけ関わらせてもらいました。このように、アスリート自身が声を上げ、現状を伝えていくこともとても、重要だと感じています」
元アスリート、母親、技術者という視点から、こうした課題を「自分事」として話す池田の姿には、並々ならぬ解決への情熱を感じることができます。
池田が語る「アスリートと生理100人プロジェクト」について詳しくはこちらから。
https://note.com/rebolt
健康についての知識を本人、親、指導者も正しく持つことが重要
女性アスリートの生理の課題の本質は、本人だけでなく、親、指導者も正しい知識と考え方を持つことができていないこと。加えてその知識を本人たちが得る環境も必要です、と池田は指摘しています。
池田「例えば、若い選手が生理のことで医療機関を探す場合、思春期外来などは一部の地域にしかなく、産婦人科は小中学生を診てくれないことがあったり、小児科では生理のことは相談しにくかったりと、いろいろな問題があります。病院で相談できたとしても、医師によっては肉体的な負担が大きいならスポーツを辞めるように指導され、そこで選手生命が左右されてしまいます」
そうならないためにも、スポーツクラブや部活単位でケアができる人材が必要であり、学校でも保健の先生からアプローチできるようなシステムがあればよいと池田は話します。
池田「心と身体を労わりながら、ずっとスポーツを楽しんでほしい。しかし生理は繊細な課題なので、まずは女の子に配慮する姿勢が大切です。家族との生活の中でどんなサービスがあれば親子のコミュニケーションをサポートできるのか。生理について親子のコミュニケーションをサポートできるアイデアがないかと思い、検討をしています。さりげなく親が娘の体調の変化に気づき、早めに相談できるようになるとよいのですが、子どもからはアクションを起こしにくい話題でもあります。どうすれば、家庭内でそれができるか。製品ありきではなく、円滑な親子関係が保たれる方向性を探る、一歩踏み込んだ調査を進めたいと思っています」
挑戦の原点は「女性が生涯スポーツを楽しめるように」

ヘルスサポートプロジェクトとして参加したSXSW
池田「いくつか現状や問題点を話しましたが、私が生理の課題に挑んだ原点は『女性が生涯スポーツを楽しめるように』という想いからです」
若いうちに燃え尽きてしまったり、健康の問題でスポーツから離れてしまう人にも再びスポーツを楽しんでもらえる社会を作りたいと話します。
池田「今は専門家と連携して情報を集めており、医師からも話を聞いています。生理はヒアリングが難しいテーマでしたが、それでも多くの意見を知ることができました。ですので、次のフェーズではヒアリングだけではなく、ビジネスモデルの検討も必要ですね。例えば生理についてのデータを集めて、健康管理アプリと連携することなどが考えられます。考え方が一致する企業があれば、協力して課題解決に挑みたいです」
元アスリート、技術者、母親の視点から池田が見ている課題にはさまざまな側面があり、まだまだ実現には高い壁がある。それでも状況に応じてしなやかにスタイルを変えながら、熱い想いが宿る挑戦を続けています。