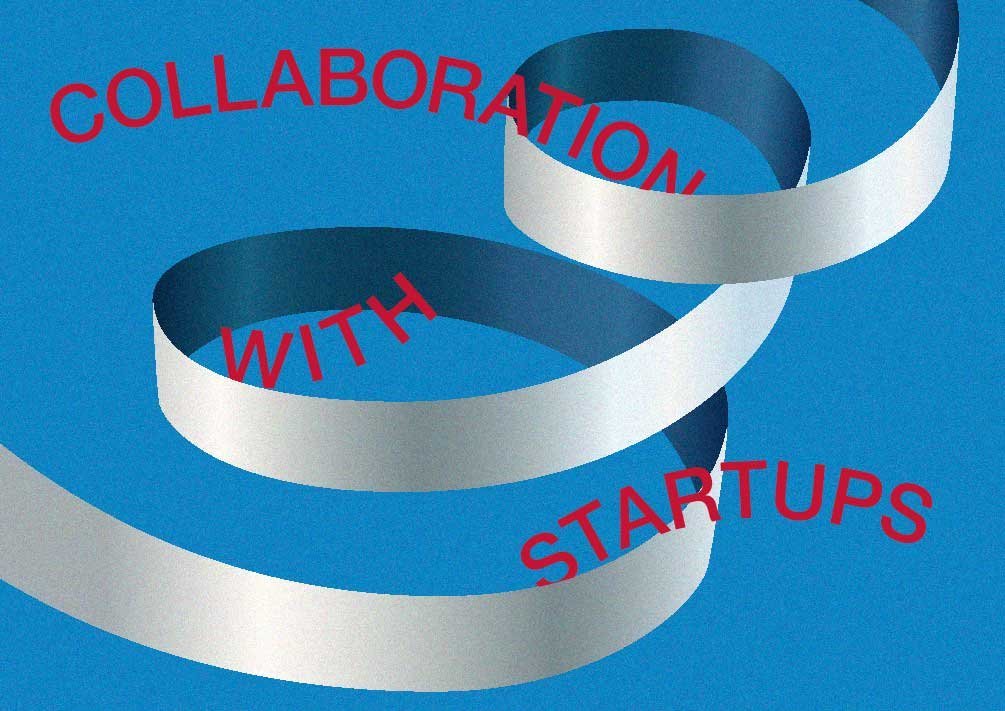Index
2月23日、私が滋賀県の家電工場を離れ、東京で訪れたのは、ダークな照明とクラブミュージックに包まれた東京ビッグサイト。フィンランド発のスタートアップの祭典、Slush Tokyo 2019の会場です。
今日ここに足を踏み入れたのは、同じパナソニックで社内起業家として活躍する仲間の姿を追うため。自分の所属する部門で新規事業開発を任された私は、Game Changer Catapultとは違う形で新規事業に挑戦しています。ですが、大きなチャレンジに踏み出せず思い悩む日々。社内に実績のない事業を提案するたびに立ちはだかる、意思決定や組織の壁。一方で、そんな壁をものともせずに、有志の応募から事業化のチャンスを勝ち取ろうとしているのが、Panasonicの社内アクセラレーションプログラム「Game Changer Catapult(以下GCカタパルト)」の選出メンバー、いわば社内起業家たちです。彼らはこの日、半年間のビジネスコンテストを経て作り上げたプロトタイプの展示に臨みました。また、Slush Tokyoの会場では、プロトタイプの展示だけでなく、ひっきりなしに選抜されたスタートアップによるピッチが行われています。自らが社会をどう変えたいかを自らの言葉で情熱を持って投資家をはじめとした聴衆に語り掛ける。それによって対話が生まれ、さらなる良いアイディアに磨き上げられていくのです。GCカタパルトも会場内のDialogue Stageにそのような対話の場を設けていました。
社内で先駆けて事業創出に挑む仲間、そして圧倒的なスピード感で社会に変革をもたらすスタートアップ集うSlush Tokyoの現場を取材することで、新たなビジネスを生み出す原動力を明らかにしたい。そんな思いから、パナソニックとともにビジネス創出に挑むキープレイヤーが集う「Dialogue Stage」を訪れました。
Forbes×Panasonic:新たなビジネスを生み出せるか、大企業が挑む戦略的オープンイノベーション
日本企業のオープンイノベーションが進むべき次のステップは「新たなビジネスを生み出せるか?」
最初のセッションでは、GCカタパルト代表の深田さんがForbes Japan副編集長の谷本友香さんをゲストに迎え、イノベーション創出の手法として多くの企業の注目を集める「オープンイノベーション」をテーマにディスカッションを繰り広げました。

谷本さんからは、「日系大企業のオープンイノベーションの課題の一つに、目的が社外の技術やアイディアを取り入れることに終始している、ということが挙げられます。私たちはさらに次のステップに進まなければなりません。その次のステップとは、新たなビジネスを生み出すことです」との課題提起がありました。「普通、上司は『自社のメリットは?』『どうマネタイズするのか?』といったことを聞きがちですが、オープンイノベーションの場において、スタートアップのCEOが投げかける問いは違います。情熱やモチベーションを社外に問うことが求められているのです。自分は何をしたいのか、自分は世界を変えるために何をしたいのか。そういう意志が人々を繋ぐことで、世界が変わっていきます。その意志さえあれば、誰でもリーダーになれる世の中なのです」と谷本さん。
GCCの挑戦:モノではなくビジネスをつくる。実は、熱意をもった社員はすぐそこにいる。
パナソニックの社内アクセラレーションプログラムGCカタパルトを率いる深田さんからは、組織の壁を越えるための、GCカタパルトの挑戦を語っていただきました。「まず、上司へお伺いを立てることをやめました。GCカタパルトでは、世界を変えられるアイディアを思いついた社員に、活動費とアドバイスを与えています」と深田さん。
また、イノベーションを起こすための人材という視点からも挑戦を続けています。GCカタパルトでは入社2年目の若手社員も活躍していると知った谷本氏から、「どうやって若手社員のモチベーションを引き出したのか」と質問がありました。深田は、「私たちは彼らを『GCカタパルトネイティブ』と呼んでいます。もともと情熱を持っていて、私たちはそれを加速させただけ」と語り、大企業で秘めた情熱を開花させる社員のポテンシャルをアピールしました。
苦しみながら形にした熱意が評価された瞬間-プロトタイプを公開した社員たちの笑顔の理由
ディスカッション終了後、深田さんに、GCカタパルトがSlush Tokyoへ出展したねらいを聞きました。プロトタイプを展示するメンバーのいきいきとした表情に、「彼らはたくさん苦しみながら思いを形にできたからこそ、今日こうして評価されることができました。これこそが仕事のやりがいだと実感してほしい」と語ります。社員の情熱を原動力に新たな事業を生み出していくステップとして、Slush Tokyoへの手ごたえを新たにした様子がうかがえました。
- ゲスト登壇者:谷本有香氏(Forbes JAPAN副編集長)
- ホスト:深田昌則(アプライアンス社Game Changer Catapult代表)

左からGCカタパルト代表深田さん、Forbes JAPAN副編集長の谷本さん
Panasonic×エイベックス & Panasonic×慶應:アイディアを、他社/大学生と共創しつづける
社内アイディアをあえて社外に出し共創する:同じ思いをもつパートナーと、一緒にビジネスを作っていきたい
2番目のセッションは、パナソニックが発案した事業アイディアとコラボレーションした2団体が登場。Slush Tokyo会場では香り関連事業の「Aromation」をエイベックスとコラボレーションしながらブラッシュアップした「Aromation 2.0」、慶應義塾大学の学生との共同プロジェクトにより「Aromation」を元に生み出された「Palbum」、「totteMEAL」を元に検討された「Letwork」が披露されていました。
この異色の共創の意図について、深田さんは、「それぞれが私たちと同じ思いを持っていたことがわかり、それなら一緒にやろうということになりました」と語ります。家電と音楽、そして大学生を結ぶ共通の思いとは何なのかを探ります。
エイベックス:未来の音楽体験を共創する:パーソナライズされた音楽体験への挑戦を語る
パーソナライズされた香りと音楽を楽しめる「Aromation 2.0」を手がけたエイベックスからは、Avex USA社長の長田さんとパートナー企業Endel SoundのEric Conyersさんが登壇。エイベックスが作る未来の音楽体験について構想を語っていただきました。
Endel Soundの取り組みは、音を通じて脳の活動をサポートするというもの。個人の心拍や時間帯、環境に合わせてカスタマイズされた音楽を届けることで、集中力強化、ストレス軽減などのセルフコントロールに役立つといいます。今後はこのメカニズムをカレンダーや交通情報と連携させ、住空間や公共空間といったあらゆる場でのサービス提供をめざしていきます。

ディスカッションする長田さん(左)とConyersさん(右)
慶應SFC琴坂研究会:感情をサポートするテクノロジーを形にしたプロトタイプを披露
続いて、慶應義塾大学 総合政策学部 琴坂将広准教授の授業を受講する学生のチームから「Palbum」を手がけた、大野雅貴さんが登壇。紹介するのは、ユーザーの声に反応して感情を推定し、ホログラムの色や香りを変える「Palbum」のプロトタイプ。将来の情報社会における、感情をサポートするテクノロジーの必要性を訴えます。「SNSから離れ、自分の感情に向き合う時間が必要」という、デジタルネイティブ世代の考える課題が形になりました。

Palbumについて語る大野さん(右から2人目)
それぞれの強み・個性が、思いもよらない化学反応を生んだ
エイベックス、慶應SFCと一緒に手がけたアイディアは、単なる商品の改良にとどまらない進化を遂げました。「香りで気持ちを整える」という「Aromation」にこめた思いに、それぞれの描く未来を掛け算して生まれた2つの事業の可能性。あるビジョンに共鳴し合う人、企業が集って思いもよらない価値を生んでいく、まさにオープンイノベーションが生まれようとするシーンを目撃することができました。
- 長田直己氏(President, Avex USA / Representative, Future of Music)
- Eric Conyers氏 (Strategic Partnerships and Business Development, Endel Sound)
- 大野雅貴さん(慶應義塾大学 環境情報学部 )
- ホスト:横田雅美さん(アプライアンス社Game Changer Catapult, Aromation事業担当)

カジトレ:社内起業家の「譲れない熱意」がビジネスを生む
ステージ上でお掃除ダンス!?「家事って楽しい!」を何より知ってもらいたい
最後のセッションは、GCカタパルトから「カジトレ」チームが登壇。事業チームの鍛冶さん、松尾さんとともに現れたのは、エプロン姿でフロアモップを持った女性たち。美そうじ®コンサルタントの清田真未さんと美そうじレディースです。彼女たちがステージ上で披露したのは、なんとオリジナルのダンス。ポップな音楽と本格的なミュージックビデオとともに、会場がオーディエンスを巻き込んだダンスフロアへと変わりました。

この「カジトレダンス」は、家事の動作を通じてシニアの筋力トレーニングをサポートする「カジトレ」のコンセプトを表現したもの。モップをかける動きやホコリをはたく動きを通じたストレッチ効果を、来場者に文字どおり体感してもらうための仕掛けだったのです。
モップ1本で、高齢化社会の課題解決をアピール
ダンス終了後のセッションでは、「カジトレ」の事業構想を語る松尾さん。単なるトレーディングツールにとどまらず、ユーザーとトレーナーとのコミュニティを作りたいといいます。さらには、「カジトレ」を通じて収集されたシニアの行動データを活用したデータビジネスをめざすと語りました。腰に巻いた「カジトレベルト」とモップ1本を携えて、世界中の高齢化問題を解決する可能性をアピールしました。

ステージ上でプレゼンする松尾さん(右)
「本気のビジネスの場」で感じた手ごたえと厳しさを胸に、事業化に挑む
前日のピッチステージに続き、二度のステージ登壇を経験した「カジトレ」チーム。鍛冶さんに手ごたえを聞きました。「投資家を前にした昨日のピッチでは、ビジネスモデルに関するアドバイスをもらいました。一方今日は、ダンスを通じて『家事って楽しい』という私たちのメッセージを伝えたかった。みなさんが盛り上がってくれたことで、コンセプトが伝わったと実感できました。」Slush Tokyoの大舞台で得た自信と課題を胸に、プロダクトの改良と事業化に挑んでいきます。
- 清田真未氏(美そうじ®コンサルタント)
- 美そうじレディースの皆さま

おわりに
3つのディスカッションを終えて、私の心に強く残ったのは、彼らの共通したメッセージです。それは、イノベーションの現場において、「熱意」や「モチベーション」が確かにビジネスを動かしているということ。Slush Tokyoとは、企業の看板ではなく、個人のビジネスにかける本気が試される場といえるでしょう。そしてこの場において、彼らの本気を笑う人はどこにもいません。たった一人でステージに堂々と立てるだけの熱意と行動が、ビジネスチャンスを掴むための資格なのです。さらに、その熱意に共鳴する人と人、会社と会社が手を取り、ビジネスを動かしていく様子を通じて、日本のオープンイノベーションの進化を目撃することができました。
セッション冒頭に谷本さんが指摘したように、新たなビジネスを生み出す際につきものなのが「本当に儲かるのか?」「事業規模は?」といった社内からの厳しい風当たり。しかし、Slush Tokyoに集った人々の口からは、そんな悩みや愚痴を聞くことはありませんでした。GCカタパルトメンバーも、年齢や所属、周囲の意見をものともせず、社員個人の譲れない熱意を武器に事業を生み出そうとしています。たとえば、「カジトレ」チームの披露したダンスは、単なる賑やかしではありません。彼女たちは、「歳をとっても、楽しく健康になれる社会を作りたい」という事業ビジョンを世間にアピールし、評価されるチャンスを自ら掴みに行ったのです。
大舞台に臨んだGCカタパルトメンバーにとって、Slush Tokyoは一つの通過点でしかありません。事業化に向けたプロダクトやビジネスモデルの改良など、社内起業家たちの挑戦はこれからも続いていきます。彼らに続いて、来年この場で情熱を語る自分の姿を思い浮かべながら、東京を後にしました。