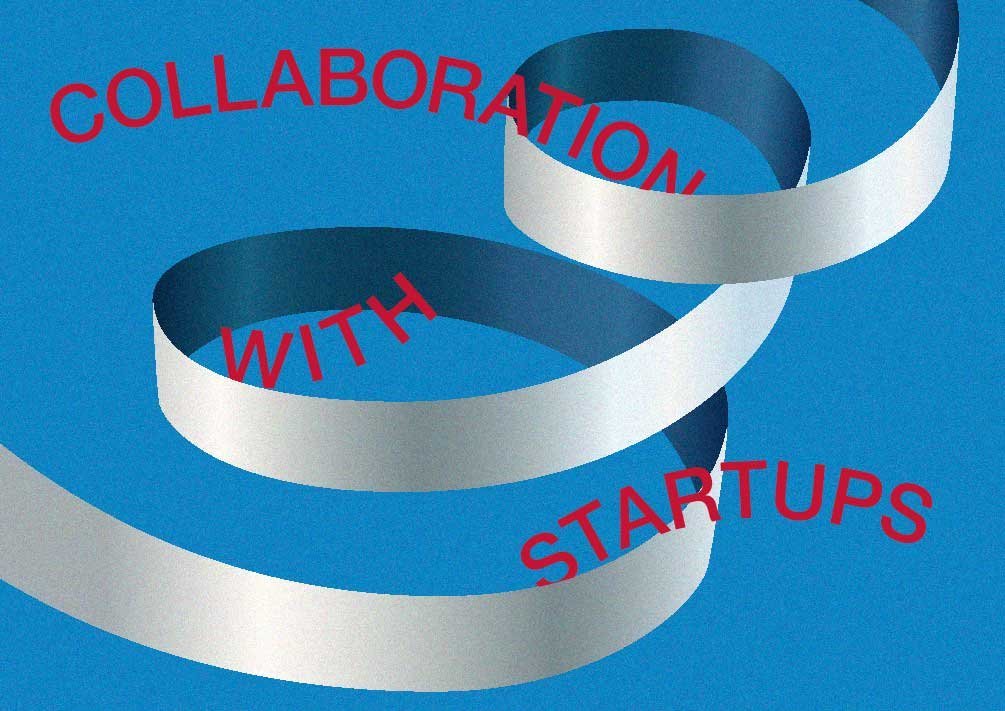Index
Game Changer Catapultの拠点は、実は東京の浜松町にあります。同じく浜松町に拠点を置いている文化放送様と一緒に、多様なアイディアを持つ人々が入り混じり、浜松町から新しいイノベーションを生み出すような場がつくれないか、という想いのもと「浜松町Innovation Culture Cafe」を開催しました。初回のテーマは「食とイノベーション」。今日はその模様をお知らせいたします。

当日の議論のファシリテーションをしてくださった早稲田大学ビジネススクール経営学博士、准教授の入山章栄先生、議論をさらに深めてくださいました
Food Techで食料問題は解決できるのか?
イベント前半は、「Food Techで食料問題は解決できるのか?」を株式会社シグマクシスの田中さん、プラネット・テーブル株式会社の菊池紳さんをお招きしてディスカッションしました。
食の課題は大きく分けて3つある、というところから議論はスタート。一つはフードロス、二つ目は食の変化に伴う環境問題、そして食生活に伴う健康問題です。特にフードロスの問題は世界中で喫緊の課題になっています。田中さんは「飢餓と飽食が両立している」という矛盾を指摘します。社会の中に飢えている人々と、食料を余らせて廃棄する人々が両立する、それは情報や経済力の非対称性の中で、需給のバランスがとられていないということではないか、と菊池さんが指摘します。パナソニック、Game Changer Catapult代表の深田は、「この問題は食に関連するバリューチェーン全体で解かなければいけない問題。多くの工程に関わっているパナソニックとしても貢献すべきエリアがたくさんあると考えている。」と語ります。
現代は大量生産、大量流通を基本とする「Food 4.0」の仕組みが限界を迎えているのではないか、それに対してどんな手立てをとれるか、ということで、田中さん、菊池さん両名の取り組みについてご紹介いただきました。
スマートキッチン・サミットジャパン
シグマクシスの田中さんからは「食Xテクノロジー」をテーマに開催されているスマートキッチン・サミットジャパンについてご紹介いただきました。

右が株式会社シグマクシス ディレクター 田中宏隆さん
「食Xテクノロジー」がテーマですが、最先端分野にこだわるわけではないこと、むしろ過去から伝承されてきた伝統をデジタルによって再定義することが注目を集めていること、Panasonicとマルコメさんのコラボレーションでスマート手造り味噌キットが生まれたことなどをご紹介いただきました。
プラネット・テーブルのサービス「SEND」
菊池さんからは農家とレストランなど、食に関わる個と個をつなぐサービス「SEND」をご紹介いただきました。

左がプラネット・テーブル株式会社代表取締役社長 菊池紳さん
食品業界平均の流通ロスが15%となっている中、流通ロス0.88%という驚異の低さを実現されています。そのカギは分散と集約の両立。SENDが自社倉庫・流通システムを持ち「集約」を進める一方で、野菜の品種や配送先のレストランなどは「分散」を実現しています。「テクノロジーとクリエイティビティの両立でそれを実現しています」と菊池さんは語ります。野菜を生産する生産者側にも、食材から多様な料理を作る消費者にも素晴らしいクリエイティビティがある、それを生かすためにテクノロジーを使って新しい食のバリューチェーンを実現されている様子を話していただきました。
「食のイノベーションは人を幸せにするのか?」
後半は「食のイノベーションは人を幸せにするのか?」をテーマに予防医学者の石川善樹先生、クックパッドの小竹貴子さんをお招きしてディスカッションをしました。

(左)予防医学研究者、医学博士の石川善樹先生、(右)クックパッド株式会社 ブランディング・編集担当本部長の小竹貴子さん
「腸が第二の脳なのではなくて、脳がは第二の腸なんだ!」という話題から「べろの洗濯機」の話題まで。話題豊富なお二人とバラエティに富んだディスカッションが繰り返され、会場は何度も爆笑の渦に包まれました。

その中で何度も繰り返されたのは、「Well-being」という言葉です。Well-beingを考えるためには、「結局自分にとっては何が幸せなのか」問いかけるべきなのではないか。例えば「家電による料理の時短」というテーマについて。家電によって料理をはじめとする家事が時短されることが価値なのではなく、「時短によって生み出された時間によって何ができるか?」が価値なのではないか。従来は消費者の時間をいかに奪い取るかの競争の時代だったが、これからはユーザーの生活のクオリティをいかに上げられるかが重要になるのではないかという議論が交わされました。
また、料理・食というものは「フードロスなどの社会課題と生活のつながりに気づく機会になるのでは」「人と人とをつなぐ役割を果たすようになるのではないか」という指摘が小竹さんからなされました。人とつながれる可能性がある一方で、孤食も社会の課題となっています。ただ「食べる・栄養になる」というだけではなく、料理をすること、食べることを通じていかに社会の中につながりをつくっていけるか、というテーマで議論が盛り上がりました。
初めての取り組みでしたが、登壇者の方、来場者の方とで非常に議論が盛り上がり、様々な人が行きかう浜松町からイノベーションが生まれる予感が強まりました。今後第二弾、第三弾も予定されています。次の機会はぜひお越し下さい。イベントの模様の一部は文化放送にて2月23日(土)19:00~19:55 OAされます。そちらもお楽しみに!