パナソニック株式会社 デザイン本部 トランスフォーメーションデザインセンター(XDC)は、2021年から未来を構想する活動「VISION UX」に取り組んできた。非日常が日常化していく未来、「自分、大切な人、地球を思いやる行動が広がっていく世界」を目指して、10年後のありたい姿を描き、新たな事業機会を探索している。
シリーズ「Make New Moment」では、「VISION UX」が描く12の未来像を起点に、「今」を捉え直すべく、さまざまなゲストと対話していく。
Index
VISION UXで向き合った社会の「ふつう」

VISION UXの「社会に織り込まれたケア(夜)」では、「『ふつう』とは何か?」について考えている。このシーンを背景に「働き方」にフォーカスし、「社会や職場で求められるふつう」を前提にすると見えにくくなる課題や個人の心の揺らぎに向き合う。
新入社員たちが、コミュニケーションや社会人としての成長に対し、どのような戸惑いを感じているのか? うつ病を発症して以降の葛藤と思索を綴られた書籍『弱さ考』(ダイヤモンド社)で、現代のビジネスパーソンに求められる強さと弱さを考察した井上慎平(いのうえ・しんぺい)さんをお迎えし、パナソニックの新入社員3名との座談会を実施した。

カメラオフの会議。業務だけの関係に「これでいいの?」
――まずは自己紹介をお願いします。
井上新卒で出版業界に足を踏み入れ、2社で書籍編集者として経験を積みました。縁あって、2019年に経済メディア「NewsPicks」の書籍レーベル「NewsPicksパブリッシング」を創刊編集長として立ち上げ、そこから約3年間、猛烈に仕事をしていたんですね。その結果、うつ病を発症し、現在も双極性障害を患っています。
僕が答えを持っているというわけではないんですが、今日は働くことについて一緒に考えたいと思っています。

竪山よろしくお願いします。くらしアプライアンス社のシェーバーやバリカン、ボディトリマーなどを扱うメンズグルーミング商品企画課に配属され、海外向けの新商品を生み出す仕事をしています。
僕は、先天性の心臓病があり、0歳の頃に手術を経験しました。そんなバックグラウンドから「今を生きる」ことを人生のモットーとしてきました。中学・高校時代は海外に短期留学、大学時代にはカナダのバンクーバーのアパレルショップで働いたこともあります。環境を変えてさまざまな価値観に触れることが成長への促進剤だと考えているので、将来的には海外で働きたいと思っています。
筧就活のようなすごい自己紹介......!
野村私は、IT・デジタル本部に配属されました。
常に自分が「楽しむこと」を大切に、学生時代の部活動はじめ、やりたいと思ったことは何でもトライしてきました。自分が達成できそうな小さな目標を立てて、挑戦を積み重ねることが好きで、そのプロセスを通じて人として成長したいと考えています。最近は、大きな目標だったパナソニックへの就職が達成できたので、現在研修中ということもあり、次の目標はまだ模索中です。目下のところ、弊社の商品サイトのシステム構想や改善を通じて、一人でも多くパナソニックファンを増やしたいと思っています。

筧エレクトリックワークス社にて、BtoB向けの製品・機器と連携したシステム開発と基盤のメンテナンスといったIT系の業務に携わっています。
学生の頃からプログラミングが好きで、大学院生時代に仲間とアプリ開発会社を立ち上げました。大学や企業から仕事を請け負ってひたすらアプリを開発し、夜中までSlackが飛び交う日々を過ごしていましたので、井上さんの『弱さ考』も興味深く読みました。新卒としてパナソニックに入社し、人間らしい生活を取り戻したようなすがすがしい気持ちで仕事に臨んでいます。
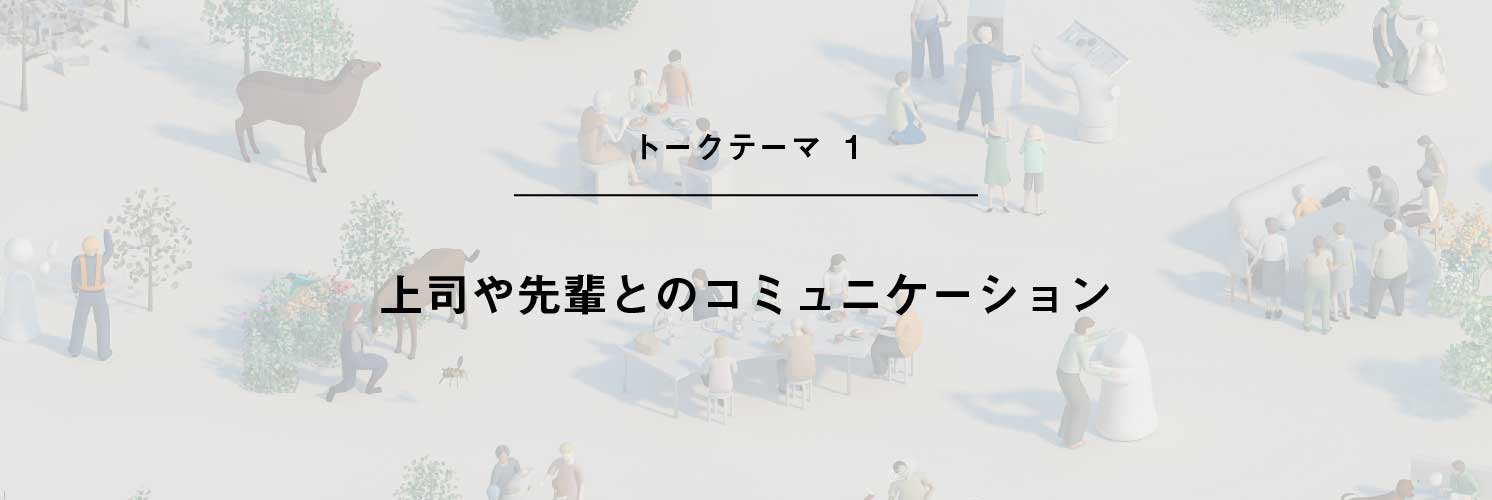
――皆さん共通の関心事項として「上司や先輩とのコミュニケーション」があるとのことで、最近感じていることを教えてください。
筧はい。僕の場合、日常的に東京と大阪を結ぶオンライン会議に参加するんですが、多くの方がカメラをオフにされているので、いまだに同じプロジェクトに携わっている方々の人物像が掴めていません。最初は興味を持っていたんですが、配属から2ヶ月が経ち、日々の仕事に支障はないので「わからなくてもやっていけるし、こういうものなのかな」という気持ちが芽生えてきました。

井上わかります、面識がなくても仕事は回りますね。そもそも属人性を排して効率化を図るのが組織ですし、リモートワークだとタスクを部分的に切り出して依頼しがちです。おっしゃっているのはきっと、仕事の全体像が見えにくいということじゃないでしょうか。
例えば、自分のタスクを先輩がフォローしてくれていたとか、トラブルが起こった時にどのように立ち回られているのかとか、後から意味が理解できてくる種類の経験がたまっていかない。今、さまざまな企業が抱えている悩みだと思います。
筧その通りだと思います。自分がシステムのひとつのパーツになったような不安を感じているのかもしれません。
竪山僕が今日参加したミーティングでも、皆さんのカメラはオフでした。効率を重視すると、自己紹介や雑談をする時間は無駄だという考え方もあるのだなぁと感じています。
ただ一方で、僕自身は「愛」がすごく大切だと思っているので、なるべく自己開示をして、信頼関係を築きながら人間味のある働き方をしたいと同時に思います。一見、遠回りのようでも、長期的には信頼関係を築く時間こそが効率を生む土台になると思っているのですが......どうでしょうか。

井上「愛」というストレートな表現も出て、職場で仕事をきちんとする以外に、情緒的なつながりも求めているんだなと実感します。
ビデオをオフにする行為は、ロジカルに業務を進めることにおいてはノイズはいらないというメッセージのひとつの表れですよね。でも、竪山さんが話したように相手の人柄や仕事に対する姿勢がわかったほうが、最終的に仕事はしやすくなるかもしれない。
一方で、職場内に情緒的なコミュニケーションへの濃淡があった場合、最近は淡の人側に合わせざるを得なくなっているので、共感しつつ難しいと思う部分もあります。仕事終わりの飲み会も、最近はあたり前ではなくなっていますね。
「Z世代の新入社員」から、「わたし」個人へ
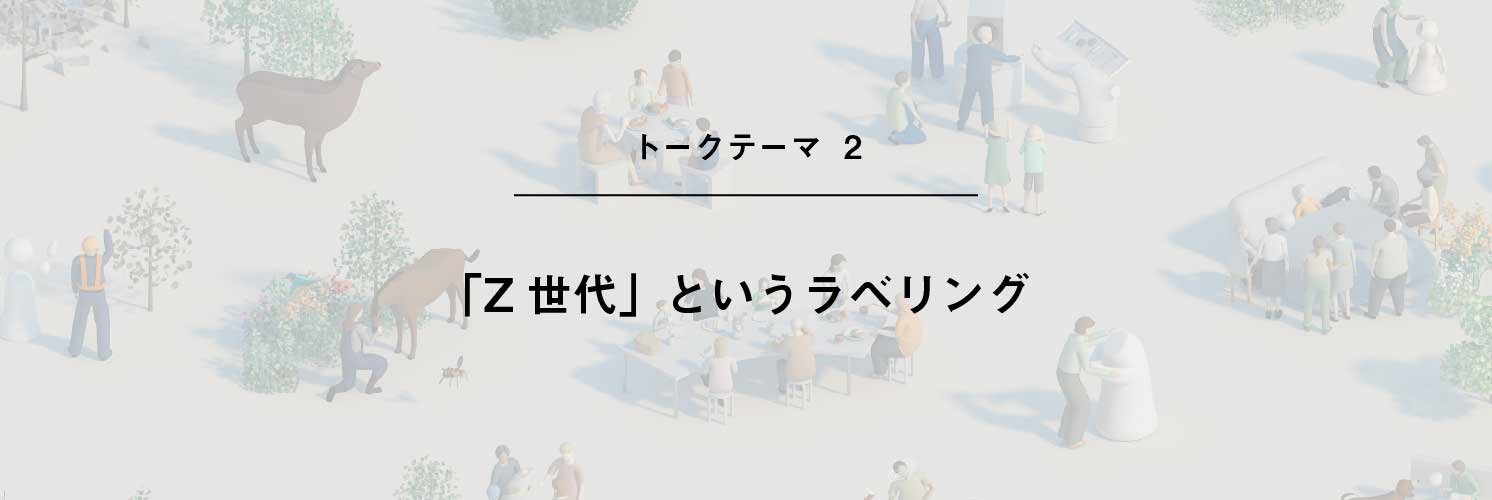
――飲み会というと「Z世代は職場の飲み会が嫌い」と聞きますが、そういった「Z世代論」を実際のところどのように感じていますか?
野村事前アンケートに「Z世代」と書いてあったので、何歳から何歳なんだろうって調べました。あまり意識したことがなかったです。

竪山世代をひとくくりにされるのは宿命だと思いつつ、Z世代という「主語」がどんどん大きくなって、僕らの知らないZ世代になっている感はあります。実際は各々まったく違う個性を持っていますし。
井上確かにラベリングは宿命なんですよね。でも安易にそうだと捉えてしまう人に対しては、おっしゃる通り一人ひとりに向き合ってほしいと感じますよね。と、かつて「ゆとり世代」といわれていた僕も思います(笑)。
野村私の上司もプライベートには踏み込まないよう意識されているように感じます。私は週明けの出社時に「お休み何してた?」って声をかけてもらったら嬉しいタイプなんですけど。
井上昭和的といわれる体育会系の縦割り組織は、年功序列の厳しい上下関係ゆえに、若手への圧力が強いという弊害があった一方で、指示や責任の所在が明確で、曖昧さが少ないという利点もありました。
そもそも日本語というのは、ひとつの言葉に二重性を持たせる曖昧さを大いに含んでいるので、キャッチボールをしていかないと相互理解が深まらないんですよね。トップダウンのわかりやすい指示系統が消滅して、「空気を読む」という曖昧さと察する文化だけが残ってしまったような気がします。
その曖昧さを打ち破るには、どちらかが一歩踏み出すしかないのかなと思うんですが、どうですか?

野村自分から上司に「お休みの日、何をされていましたか?」と訊ねるのもなかなか勇気がいりますが......お伺いして大丈夫ですかね?
井上上司の方も同じ気持ちだと思いますよ。勇気を出してみたら案外大したことなかったっていうことはたくさんありますし。
筧自分の話を先に持ち出せば、「聞いてもいいのかな」って思ってくれそうじゃない!?
井上10歳とか20歳離れると、カテゴライズされた「飲み会はあまり好きではないらしい」のようなところから入らないとコミュニケーションが成立しにくいから、まず知っておきたいっていう前向きな姿勢も含んでいると思うんですよ。
「でも実は自分はこういうところもあって」という会話からはじめて、Z世代の新入社員の一人から、竪山さんや野村さん、筧さんっていう個人に焦点が絞られていく。そういったコミュニケーションができたらいいですね。
だから、皆さん側からどんどん踏み出してほしいです。

筧実は、今の状況を打破しようと自分なりに一歩踏み出してみたことがありまして。他の方がカメラオフ状態のなか、僕だけカメラをオンにしていました(笑)。
井上え! いいですね。
筧竪山さんと野村さんはカメラをオンにしてみたことある?
野村したことないです。
竪山僕も。
筧やってみて。他の出席者に少し驚かれるかもしれないけど、発言できるし、質問もしやすい気がしました。
井上今年の新卒はやたらオンにしてくるなって、広まると面白いな(笑)。
変化が速すぎて、スパンの長い「いつか」は待てない
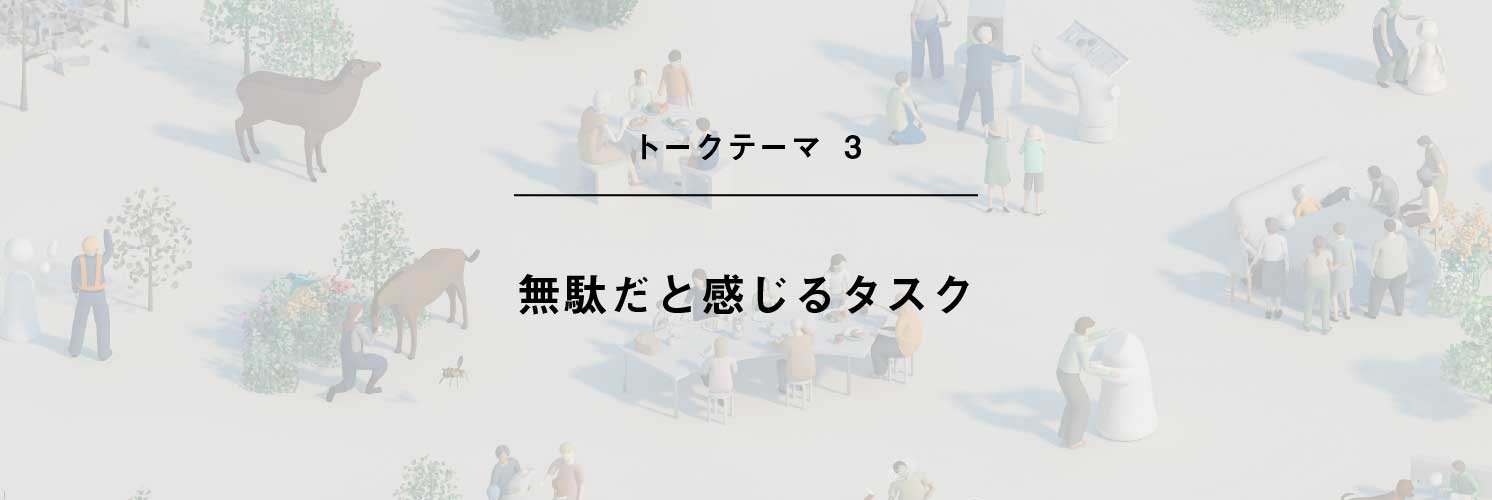
竪山コミュニケーション以外に、常々疑問に思っていることがあるんですが。会議なども含め直接自分に関係のない業務に関わる際、どれぐらい熱心に取り組むべきでしょうか。タスクが溢れるなかで成果をあげるには、限られた時間とエネルギーを「本当に重要なこと」に注ぐべきであると、とあるビジネス書で読みました。

井上関わりの薄そうなタスクに時間を割くのは、なんとなく無駄に感じるということですね。
筧確かに、研修でも無駄を省くことを心がけるよう教えられました。業務の中にはいろいろ無駄に感じるものもあったりしますが、上司にはなかなか言いづらいです。
井上なるほど。皆さんにとって「無駄に感じる」判断軸ってどこにあるんですか?
野村私の判断基準は、恣意的かもしれませんが「役に立つかどうか」かも。「今の仕事につながりそう」と感じたら身が入ります。一方で、つながりを見出せないことはさらっと完了させてしまいますね。「いつか役に立つ」という言葉をよく耳にしますが、その考え方が私には難しく感じます。
筧僕もそうかも。趣味のアプリ開発では、AIを使って効率的に済ますこともできますが、役立つことなら手を動かしてプログラミングしますし、時間をかけても一向に構いません。
竪山僕は、成果への貢献度ですかね。その業務が成果やアウトプットにどれだけ影響を与えているかどうか。
井上このテーマ、面白いですね。「無駄とは何か」というと、実際は事後的にしかわからない。「いつか役に立つ」って言われても、その「いつか」っていつなんだと。
実のところ、テクノロジーが加速度的に進化して、「いつか」のタイムスパンもどんどん短くなっています。以前はひとつの職を勤め上げるのがふつうでしたが、今は違います。数年後には、せっかく習得したスキルが役に立つどころかAIに置き換えられているかもしれませんし。皆さんに以前のように長いスパンの「いつか」を待つように求めるのは、正直、酷だと思います。だから、頑張ろうとしても頑張れないタスクはさらっと済ますという選択もすごくよくわかりますね。
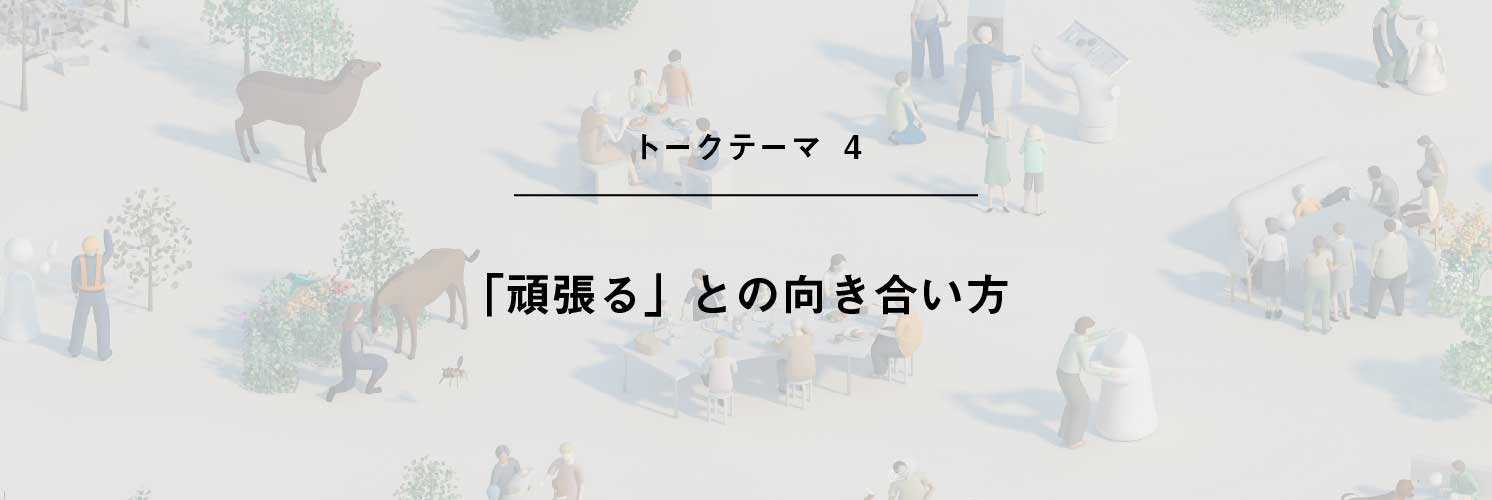
筧「頑張る」に関連して、僕からもいいですか? 井上さんは『弱さ考』のなかで「本気で頑張ったけど、強くあり続けられなかった」ことを書いていらして。でも、人がギリギリまで頑張る姿は、やっぱり綺麗だと思うんです。一方、最近の自分を省みると、頑張りきれていないかもしれないと感じていて。

井上「頑張る」って成長することや能力を獲得すること、あるいは「自分、頑張れてるな」っていう満足感を得ることであったり、色々な見方ができると思うので、何が正解とかはないですよね。
ただ僕からいえるのは、社会の構造や組織のあり方が急速に変化したことで、多くの人が切迫感をもって「成長し続けなければ」と思い込むようになったということです。それで頑張れているときはいいんですが、思いもかけない理由で、頑張り続けることができなくなる時がくるかもしれない。そんな時でも、自分を責める必要は全くない、ということだけは伝えておきたいです。

井上一方で、がむしゃらに頑張るのが良くないということでもないです。以前、生命科学者でもあり起業家でもある高橋祥子さんの書籍『生命科学的思考』に編集として携わったんですが、そのなかで「視野は広く、もしくは狭く限定するものではなく、調節できることが大切」だとおっしゃっていました。
20代は視野を狭くできる貴重な期間だと思います。今湧き上がる感情には今向き合わないと、後から取り戻すことはできません。皆さんの頑張りの定義は各々ですが、頑張りたい人は思いっきり視野を狭く、自分の思うがままに邁進してほしいと思います。
筧なるほど......、今日はありがとうございました。普段このような話をすることがないので、非常に貴重な機会をいただきました。仕事におけるさまざまな事柄に、絶対的な正解というものはないんだと気づきが得られました。
竪山僕も、自分にとっての成長や働き方について、言語化する難しさを感じたとともに、あらためて考えてみる良い機会をいただいたと感じました。
野村初めてお会いした皆さんといろいろと深い話ができて有意義な時間になりました。今後は上司や先輩の方々、そして社外の方々と信頼関係を築くためにも、積極的な行動を心がけていきたいと思います。
「ふつう」を問い直す対話が、いつか誰かのためになる
ひとつの正解を求めるためではなく、共感し、驚きながらお互いの考えに耳を傾けあった座談会。こういった話は「意識高い系」に見える気がして普段はしづらいとこぼしていた新入社員の3人から、多くの本音がこぼれ出し、井上さんがしっかりと受け止めてくださいました。
今回VISION UXの「社会に織り込まれたケア(夜)」を背景に、社会人の新たな「ふつう」について考えてきました。「働き方」をはじめ、社会で形成された規範を前提とすると見えにくくなってしまうことは至るところに存在しています。それぞれの戸惑いや困りごとを知るには、座談会で4人が語り合ったように、まずは一歩踏み出してコミュニケーションをすることが重要です。
そういった対話が、例えば年齢や職業といったラベルを取り払った、等身大のその人を理解することにつながっていくのではないでしょうか。

Information

VISION UX
「自分、大切な人、地球を思いやる行動が広がっていく世界」を目指し、新たな事業機会を探索するため、10年後のありたい姿を描くプロジェクトです。
街の再建、避難所、共助コミュニティ、夜の街、最期の迎え方など、未来に向けたアクションを議論するための、具体的なシーンを紹介しています。
Profile

筧 万里(かけひ・ばんり)
パナソニック株式会社 エレクトリックワークス社 電材&くらしエネルギー事業部
2025年入社。エレクトリックワークス社にて、IoT向けのITシステム開発や基盤のメンテナンスといったIT系の業務に従事。
私のMake New|Make New Application
世界中の「困った」を解決するソフトウェアを提供します
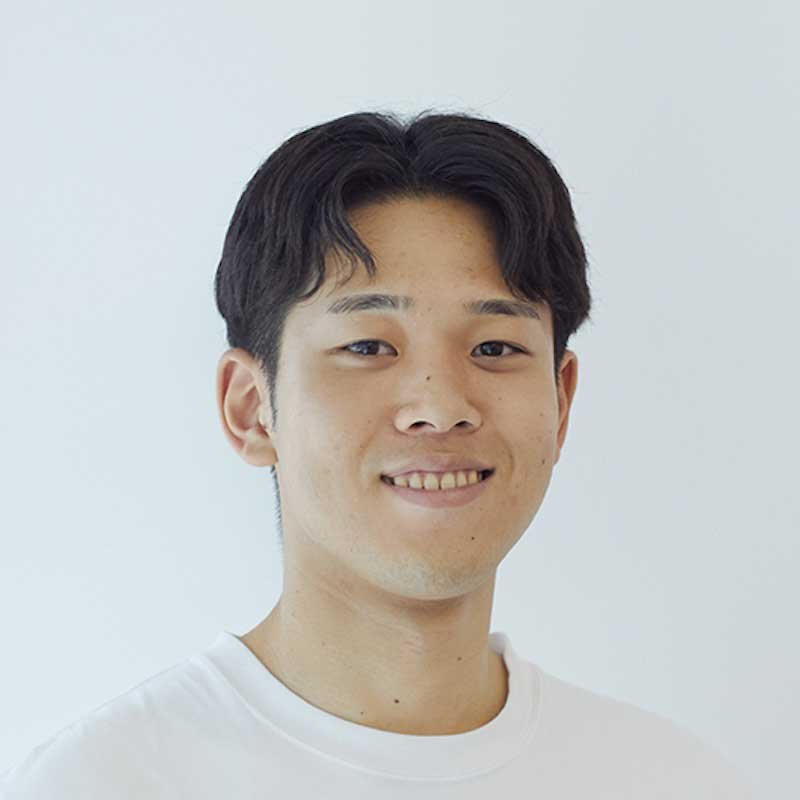
竪山 開(たてやま・かい)
パナソニック株式会社 くらしアプライアンス社 ビューティ・パーソナルケア事業部
2025年入社。くらしアプライアンス社のメンズグルーミング商品企画課に配属。シェーバーやバリカン、ボディトリマーなどを扱い、海外市場向けの新商品企画を担当。
私のMake New|Make New Value
パナソニック製品をより多くの国と地域に届けたい

野村 采加(のむら・あやか)
パナソニック株式会社 IT・デジタル本部 CRMアーキテクトセンター
2025年入社。IT・デジタル本部に配属され、パナソニックの公式商品サイトのシステム構想や改善業務に従事。
私のMake New|Make New Connections
Panasonic製品と価値ある出会いをお客さまへ

井上慎平(いのうえ・しんぺい)
株式会社問い読 共同創業者、NewsPicksパブリッシング創刊編集長
1988年大阪生まれ。京都大学総合人間学部卒業。ディスカヴァー・トゥエンティワン、ダイヤモンド社を経て2019年、ソーシャル経済メディアNewsPicksにて書籍レーベル「NewsPicksパブリッシング」を立ち上げ創刊編集長を務めた。
代表的な担当書に中室牧子『学力の経済学』、マシュー・サイド『失敗の科学』(ともにディスカヴァー・トゥエンティワン)、北野唯我『転職の思考法』(ダイヤモンド社)、安宅和人『シン・ニホン』(NewsPicksパブリッシング)などがある。2025年、株式会社問い読を共同創業。








