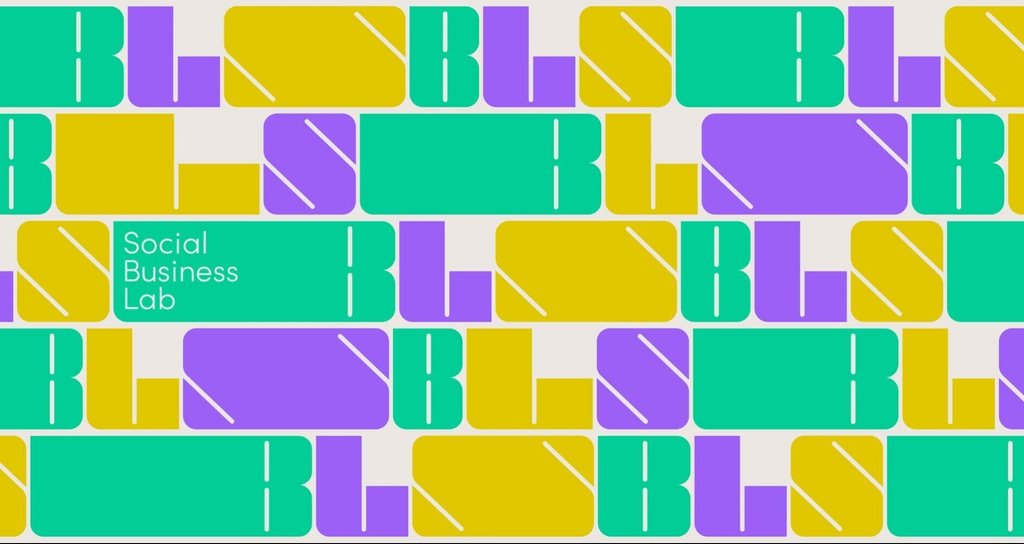Index
「家族」という言葉を聞いて、どんなイメージを思い浮かべるでしょうか。多様な個人がいるように、家族のありかたも無数に存在していますが、たとえば企業の発信という視点で考えてみると、広告を通して描かれる「家族像」はまだまだ単一的で限定的な表現にとどまっています。また、社会の構造において周縁化されてきた人たちのくらしに寄り添ったサービスや商品はいまだ不足しています。そのような状況において、ものづくりやサービス提供を行なう企業は、社会が抱える課題をどう具体的に実装していけばいいのでしょうか。
パナソニック株式会社のふつう研究室と、ほか2社で運営されている「Social Business Lab」は、2023年10月に『企業が発信する家族像とマイノリティ - Frame in Project -』というイベントを2回にわたり開催。
「個人と個人の対話を出発点に、遠くの誰かにまで想像や語りを広げる」ことをミッションに掲げる株式会社ミーアンドユー(me and you)の野村由芽さんにレポートしてもらいました。


「無意識の排除」をしないために
わたしはいま、me and youという会社を二人で立ち上げ、運営しているのですが、そこでは二つの事業を軸に置いています。一つは、メディア・コミュニティの運営や出版、ラジオ・Podcastなどの自社事業。ここでは、「『わたし』と『あなた』という小さな主語で向き合える関係性や社会」にまつわる考えや価値観を発信したり、「なかったことにされてしまう」違和感や問いを、安心しながら自分の言葉で話しはじめてみる場所づくりを行なったりしています。もう一つは、さまざまな企業のブランディング・コンサルティングや、広報宣伝のためのコンテンツ制作、広告のクリエイティブ制作などの、いわゆる「クライアントワーク」です。
メディア・コミュニティ運営だけではなかなか収益を生み出しづらく、生計を立てるのが難しいという側面はあるものの、クライアントワークに積極的に取り組んでいる背景には、「企業」がわたしたち一人ひとりの個人的な生活や生き方にもたらす影響力の大きさに目を向け、かかわりたいという気持ちがあります。
たとえば広告表現においては、単一的な家族像やジェンダーロールや規範を強化するような表現がまだまだ多く見られます(小林美香さんの『ジェンダー目線の広告観察』に詳しく書かれているので、ぜひ読んでいただきたいです)。また、くらしや社会のなかで「あたり前」とされているモノの具体的な形状ひとつをとっても、無意識のうちに誰かを排除してしまっている状況にあります。それは企業がこれから「取り組むべきこと」であり、裏を返せば当然、企業が「できていないこと」でもあります。
そんな現状に対して、企業として何をしていけるのか、企業のなかの人が何を考えているのか、聞いてみたい。そこを突破する糸口を見つけたいという気持ちで会場に向かいました。
『企業が発信する家族像とマイノリティ - Frame in Project -』
イベントの前半は、人権や社会問題に関わる人たちによる「当事者の声」を伝えるゲストトーク。後半は、グループに分かれてのディスカッションという構成でした。

10月4日に実施された第1回のテーマは、「社会的マイノリティ当事者が直面するフレームアウトの実情」。「クォーター」として生まれ育った背景から、「ハーフ」や「ミックス」「ダブル」などを研究する下地ローレンス吉孝さんと、トランスジェンダー当事者でありCODA(Children of Deaf Adults / 耳が聴こえない、あるいは聴こえにくい親のもとで育った子どものこと)であるかなたいむ。さんが登壇。それぞれが、家族という視点で見たときに「フレームアウト」されたと感じた経験を語りました。
第2回は、「家族から見たマイノリティ 〜家族の日のプロモーションを考えよう〜」というテーマで開催され、ダウン症のある娘を授かったフリーアナウンサーの長谷部真奈見さんと、知的障害(※1)のある人たちの作品をプロダクトやアートに昇華させる取り組みを行なう株式会社ヘラルボニーの伊藤琢真さんがゲストとして登場。今回は、わたしが参加した2回目の様子をじっくりレポートしたいと思います。
※1 今回の記事では、障害を社会モデルとして捉えているという立場で「障害」という表記を使用しております。
「障害がある」ことで分断させられる社会
まず長谷部真奈見さんが、娘の写真をスライドに写しながら、話し始めました。
長谷部親バカなんですけれど、かわいいでしょう?うちの娘は、ダウン症をもって生まれてきました。こんなにかわいいのに、娘を産んだ当初は、すごくしんどかったんです。その経験から、このしんどさの背景には何があるのかを考えたくて、向き合い始めました。

当時は長谷部さんにもダウン症についての知識がなく、「しゃべれるようになりますか?」「歩けるようになりますか?」「この子は笑ってくれますか?」など、医師に立て続けに質問したそう。「要するに、『何もできないんじゃないか』と思ってしまっていた。知識がなかったんですね」。また、当時は病院関係者からも「残念ながら......」「お母さん、検査しなかったんですか?」「若いから次いきましょう。次がんばりましょう」と声をかけられたと話します。
長谷部娘とくらすうちに、当時の自分が想像していたよりもずっといろんなことができるのだと気づきました。金澤翔子さんというダウン症のある書家の方が素晴らしい作品を発表されていて、セブンイレブンの広告にも起用されているのですが、ダウン症のある人たちには、できることや、面白いところがたくさんあるんです。FunnyではなくInterestingである面白さが社会に知られていないと実感して、仲間とともにNPO法人アクセプションズを立ち上げました。
アクセプションズの活動の具体例として紹介があったのは、世界ダウン症デーに子どもメガネのアンファンとタイアップして開発した、鼻の凹凸がなだらかであるという特徴にあわせた「ずれにくいメガネ」。それは結果的にダウン症のある子どもたちのみならず、広く普及して大ヒット商品になったと言います。

長谷部さんの娘は、現在高校入学を控える年齢ですが、日本のいまの制度では特別支援学校の高等部に通うという進路しかなく、悩んでいると話します。「いまは家族もろとも、分けられてしまうシステムになっているんです。障害があるからと一人ひとりを決めつけないで、社会として個人をインクルードした状態で、個性が発揮できるようになってほしい」という言葉でトークを結びました。
「支援する」のではなく、事業を「一緒につくる」
続いて登壇したのは、ヘラルボニーの伊藤琢真さん。思わず「素敵ですね」と声をかけたくなるような総柄のシャツは、障害のある作家さんが描いた絵をあしらったもの。ヘラルボニーは、アート活動に取り組む福祉施設や、個人で活動している知的障害のある作家と契約し、アート作品をデータとして預かったうえで、さまざまなかたちで社会に実装する活動を行なっています。
伊藤僕たちは障害のある人たちのことを、あえて普通じゃないと断言したうえで、「異彩を、放て。」というミッションを掲げています。障害がある人がつくったものは、いくら素敵だったとしても正当に評価されていない部分があると思っています。けれど、知的障害のある人のなかには、朝から晩まで同じことをずっと続けられる集中力があったり、手先がとても器用だったり、障害があるからこそ描ける世界観があったりするんです。
そこでヘラルボニーでは、障害と社会のタッチポイントをつくることで、福祉を起点に新しい文化を生み出し、障害のある人たちの可能性にリスペクトを持ちながら一人ひとりのありのままを肯定できる社会を目指しています。

「ヘラルボニー」というユニークな響きをもつ社名は、創業者であり、双子の家族でもある松田崇弥さん、松田文登さんの兄・翔太さんが、自由帳にずっと書いていた言葉からとったもの。知的障害を伴う自閉症のある翔太さんは、二人にとってはずっとあたり前の家族でしたが、学校に通い出した頃から兄に障害があることでからかわれたり、親戚に「翔太さんの分まで頑張って、二人は生きていくんだぞ」といった言葉をかけられたりするようになったそう。社会というフィルターを1枚通した途端、「かわいそうな存在」「欠落している存在」となってしまうことに違和感を覚えたことが、ヘラルボニー創業の出発点になりました。
ヘラルボニーの特徴は、その社会的な課題意識を支援という文脈ではなく、利益を生み出す会社として事業化しているところです。
伊藤福祉施設の人々がつくった作品は、道の駅のような場所で、原価に近い値段で売られていることが多いですよね。ヘラルボニーでは、アートのライセンスというかたちで事業を行ない、支援のために買うという動機ではなく、まず「アートとして素敵だ」という入り口になるように気をつけています。
現在、就労継続支援B型事業所(※2)に通っている障害のある人たちの工賃は、全国平均で大体月16,000円ほど。アート作品として価値を高めることでお金を生み出し、作家さんに報酬としてお支払いするシステムをつくっているんです。
あとは、作品の見せ方にもこだわっています。障害のある方が描いた作品は、役場などで小学生の人たちが描いたものと並べて展示される場面をよく見かけます。それが悪いということではないのですが、作品の見せ方によって見られ方は大きく変わってきます。ヘラルボニーは自分たちができるやり方として、たとえば東京駅の八重洲口の切符売り場や、ハイアット セントリック銀座のスイートルームなどでも作品を展開してもらうなど、飾る場所や飾り方にも気をつけています。
※2 就労継続支援B型事業所とは、一般企業に雇用されることが困難であって、雇用契約に基づく就労が困難である者に対して、就労の機会の提供及び生産活動の機会の提供を行なう施設のこと。

伊藤さんは「『障害』というふうにざっくりと捉えるのではなく、『その人自身はどんなことができるのか』ということにフォーカスしていくと、さまざまな働き方を見つけ出せるのではないかと思います」とも語ります。
ヘラルボニーは、マジョリティが一方的に決めた「できる人」「できない人」という基準で個人をわけることをせず、「(障害のある)作家は作品をつくることで生計を立て、企業は利益を出す」という仕組みを一緒に生み出しています。それがひいては一人ひとりの生きやすさの実現にもつながるという、ある種の水平な共同体として事業を成立させている姿が印象的でした。
前半のトークで長谷部さんが話していたように、個人的なものとして障害を捉え、医療によって対応を行なってきた「医学モデル」から、障害は社会のあり方によって生み出されているものであり、障害があることによって生じるさまざまな障壁をとりのぞくのは社会の責務であるという「社会モデル」に現在は変化しつつあります。
しかし、長谷部さん、伊藤さんの話からも、物理的・制度的・アクセシビリティの観点・心理的な側面において、マジョリティとは異なるとみなされた身体、環境、立場の人たちへのバリアが存在し続けていることが明らかであり、それは自分も含めたマジョリティの問題です。そしていまの社会は「できる」人にはますますチャンスがもたらされ、「できない」人はどんどん無力化されていく構造になっています。長谷部さん、伊藤さんの話には、社会的障壁に直面させられているマイノリティの人たちのアイデンティティを尊重し、個人の人間性を見つめて向き合うあり方の実践がありました。わたしもあなたも誰もがマイノリティになり得る社会において、そのほうがずっと息のしやすい社会である。そうした思いを強く抱いたトークでした。
課題意識を企業活動につなげる難しさ
後半は、異なる企業でそれぞれにDEIなどの活動に取り組む担当者たちが、グループごとにディスカッション。ゲストトークでの気づきや、自分たちの会社はどんな社会問題に向き合い取り組んでいけるのかというアイデア、実現の過程にある悩みやハードルについて話し合いました。

わたしが参加したグループで共通していた課題意識は、「思いはあれど、かたちにすること」の難しさ。社内で提案する人がいたとしても、受け取る側の準備ができておらず、その提案に対して「(できていない)自分が責められているように感じ」、受け止められない状況があるといった例をもとに、「受け取る人のキャパシティをどう広げるかが大事」という声が挙がりました。

金銭的な利益を右肩上がりに生まなければならない、行き過ぎた資本主義の構造が維持されようとしてきた企業環境においては、「マジョリティ」に向けて商売をしたほうが儲かると考えてしまう構造の根強さゆえに、異なる一人ひとりの差異に目を向けづらい状況が維持されてきてしまったのではないかという仮説を個人的にも持っていました。それをどうしたらいいのか、企業のなかにいる人に聞いてみたいと思い、質問しました。

印象的だったのは、「まずはできるだけお金をかけずに簡易的なプロトタイプをつくって、効果検証のサイクルをスピーディーに回す」という意見。アイデアが浮かんだら、一緒にそのプロジェクトを動かすメンバーを見つけ、小さくてもテストマーケティングを行ない、それに反応してくれる人を可視化する。「人だまりをつくる」ことで初めて、課題に対する需要が目に見えるものとして社内でも認識され、実際に使えるお金が増えていったという話には、ほかの企業の方から「自社でも取り入れてみたい」という声が挙がりました。
また、同様に利益という観点だと「目の前の売り上げもほしいけれど、たとえばメディアに取り上げられたり、ブランディングにつながることで、結果的に広告予算の支出が減ったり、あるいは人事的な採用につながったりすることがある」という実績の共有も。短期的な売り上げのみで判断するのではなく、生み出した価値を人的資本とつなげて考え、その価値観を社内にしっかり説明することの大切さも語られました。
企業同士でつながることと、n=1の個人と向き合うということ
最後に、イベントの最後に個別にインタビューした、参加者の声を紹介します。
わたしは普段NPOもやっているのですが、社会がとりこぼしてしまっている人たちの状況に対して、非営利の団体がどうにか頑張っているみたいな状況があるんです。だけど、本当は企業がそこに向き合えば、とりこぼされる人がもっと減っていくはずで。だからこそ今日のように企業のなかのひとたちと横のつながりをつくって関わりをもちながら、企業が向き合うべきソリューションを探究する場はとても大事だと感じました。
ひとつの企業のなかだけだと組織やお金の面で進みが遅いこともあるから、同じような問題意識を持っている別の企業の人たちと一緒にやれるといいなと感じたことが今日の大きな気づきでした。今日みたいに複数の企業が集まれば、財団や投資家の人に関わってもらって事業をつくることもできるんじゃないかと。社内に持ち帰れることとして、既成概念を問う人が増えれば、新規事業が生まれるのだろうという気づきもありましたね。社員の誰がそういった問いを持っているのかが可視化される場をもうけて、問いをひっぱり出すことでアクションにつなげたいです。

マイノリティとされる人たちを「何かができない」とするのではなく、わたしたちの会社では「n=1と向き合って課題を見つけていく」という言い方をしています。一人ひとりの課題を見つけると、多分それは社会が抱えている大きな課題につながることが多いと思うんですよ。
フレームを点検し、自分がすべきことを考え続ける重要性
今回のワークショップでは、「フレームイン」「フレームアウト」という言葉が使われていましたが、そもそも「フレーム」という概念が、「社会はこうあるべき」という一人ひとりの思い込みによってつくられた不完全なものです。それを自覚することから始める必要があると参加を通じて強く感じました。そのフレームは、「壁」とも言い換え可能であり、何かと何かを分け、一方を疎外する壁をマジョリティの一人ひとりが維持してきたことで、社会の仕組みやコミュニティから自分と異なる人をはじきだし、おしやってきました。その事実に向き合うことで初めて、それぞれの持ち場で「フレーム/壁」をつぶさに点検し、取り除き、個人の生がのびやかにあれる社会を目指す出発点に立てるのだと思います。
参加者の一人が話していた「人がついてこなかったら、会社は立ちいかなくなる」という言葉は、今回のイベントで心に残ったものの一つです。利益を生む必要がある企業という環境においても、何よりも「人」、つまり一人ひとりの人権を尊重し、どんな立場であっても生きていける仕組みや環境つくることが、企業の存続や発展においても重要なのではないでしょうか。マジョリティが変化することなしに「包摂」を謳うような、都合のいい「多様性」を掲げるのではなく、いまいる場所から見える景色を疑い、自分がすべきことは何かを考え続けること。今回のワークショップのように、その問題に直面させられている当事者性のある人の話を聞くことや、一緒に時間を過ごすこと、本や映画から学ぶこと、そこから考え対話することも、自分の考えや知覚を揺さぶられ、変化につながるための具体的な行動の一つであり、わたし自身も日々のなかで継続して取り組んでいきたいと考えています。
一人ひとりが初めに取り組めるのは小さなことからだったとしても、その個人が撒いた種を育て、遠くまで運ぶ役割を担うのが、企業というものに宿り得る希望だと感じています。これからの企業が、一人ひとりの生きる尊厳を決して手放さずに進んでいく責任を果たすことを願って、レポートを締めくくりたいと思います。
【関連記事はこちら】
Profile

野村 由芽(のむら・ゆめ)
編集者。2017年にCINRA同僚の竹中万季と“She is”を立ち上げ、編集長を務める。2021年、個人と個人の対話を出発点に、遠くの誰かにまで想像や語りを広げるための拠点としてme and you, inc.を設立。個人的な想いや感情を尊重し、社会の構造まで考えていくメディア・コミュニティ「me and you little magazine & club」を運営するほか、性について自分の温度で話しはじめてみる音声番組「わたしたちのスリープオーバー」をJ-WAVE Podcastで配信中。