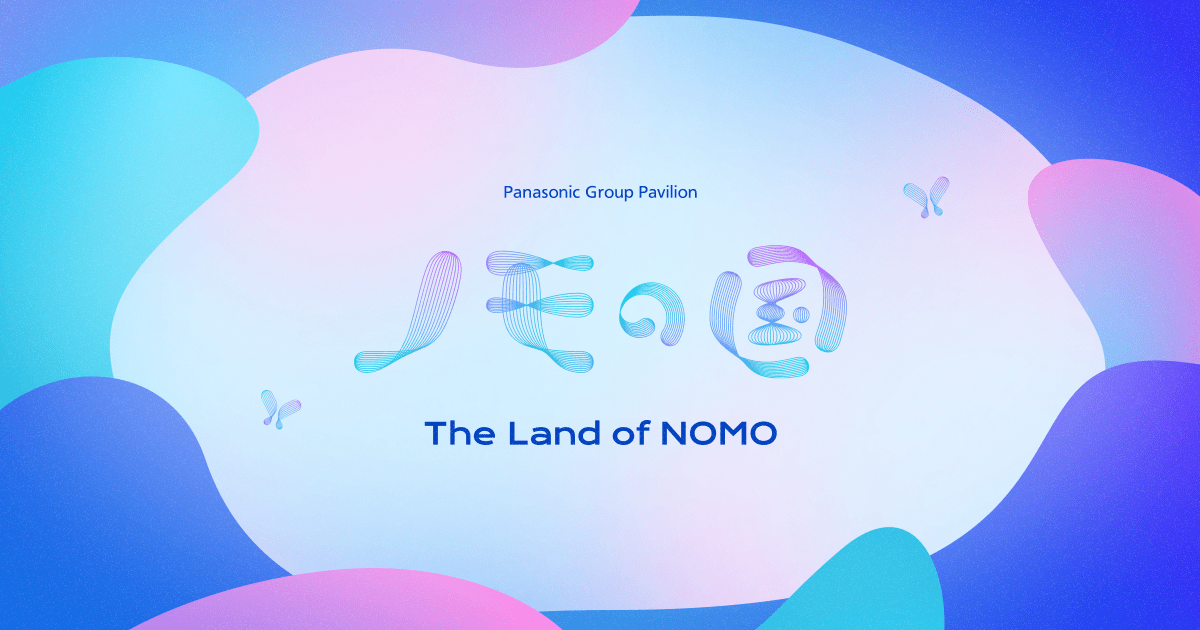新しい時代を生きる二人に今のパナソニックについて感じること、そして未来のパナソニックへ期待することを自由に語っていただく本企画「拝啓、パナソニック」。
今回のゲストは、PASS THE BATONなどの実業に加え、「文喫」「ヤエスパブリック」のプロデュースも手掛けてきた株式会社スマイルズ代表取締役社長兼CCOの野崎亙(のざき・わたる)さんと、東急歌舞伎町タワーや『2025年日本国際博覧会(大阪・関西万博)』のパビリオンの建築設計などを担当してきた建築家の永山祐子(ながやま・ゆうこ)さんです。
Make New Magazineの記事を読んで感じたことから、パナソニックのこれからに対する期待まで、パナソニックとも関わりがある二人ならではの視点で語り合ってもらった。
Index
誰も気づかないくらい、あたりまえのことを
――パナソニックとの関わりも深いお二人に、まずはパナソニックが2022年から掲げているアクションワード「Make New」についてお伺いします。「Make New」には未来のくらしの定番となるような製品やサービス、ソリューションを生み出すという決意が込められています。この言葉と実際のパナソニックの活動を照らし合わせて、感じることはありますか?
野崎新しい定番をつくる、新しい価値をつくるというと、世界をひっくり返すような革命的な取り組みに感じられるかもしれません。ただ、パナソニックが掲げている「Make New」はそんなに派手なことではなくて、もっとあたりまえのこと。新しい生活のインフラをつくるといった、誰も気に留めないようなことに、実直に取り組んでいくという意味なのかなと捉えています。
たとえば、スイッチ・コンセントなどもそうですよね。今では日本国内のシェアの多くをパナソニックが占めていますが、スイッチを押すと明かりが点く、コンセントにプラグを挿せば電化製品を使える、といったことはあたりまえすぎて、誰も気に留めていません。
こうした誰も気づかないくらいあたりまえのインフラを安価かつ安全に提供する背景には、かつて松下幸之助さんが提唱した「水道哲学」(※)という考え方もあるのだと思います。そういう意味では「Make New」という新しいスローガンも、パナソニックが100年前からやってきたことの延長線上にあるのかなと。
※ パナソニック創業者・松下幸之助が提唱したと言われている経営哲学。商品を大量生産・供給し、価格を下げることで、人々が水道の水のように容易に手に 入れられる社会を目指す考え
永山野崎さんがおっしゃる通りだと思います。万博のプロジェクトでも、ご一緒した社員の方々はパナソニックが100年にわたって大事にしてきた「哲学」を持っていると感じました。
そもそも「ノモの国」のコンセプト自体が、「モノとこころは写し鏡のような存在である」という松下幸之助さんの考え方から生まれたものです。創業当時からの理念が今日まで貫き通されているのは、本当にすごいことだと思います。また、そんな普遍的な哲学がある一方で、最近のパナソニックには大きな変化も感じます。

――具体的に、どんなところに変化を感じますか?
永山顕著なのは、デザインに対する考え方です。私は仕事柄パナソニックの電設資材の分厚いカタログを見るのが好きなのですが、スイッチやコンセントといった配線器具、分電盤、ブレーカーなど、本当に数多くの製品があります。ただ、バリエーションが豊富すぎるがゆえに、これまではあまりデザインの統一がなされていないと感じることもありました。建築家としては、わずかな仕上げ、角Rの寸法の違いでも、気になってしまうんです。
それが最近では、パナソニック全体で同じデザイン思想を共有し、これまでバラバラに開発してきた電設資材の規格とデザインを統合していく動きがあると聞きました。会社の規模が大きいので簡単なことではないはずですが、大きく成長した組織に横串を刺して同じ方向を目指していくのは素晴らしいことですし、いずれはそれが日本の空間の質の底上げにつながるのではないかと思います。

Archi Designは、視覚的なノイズを徹底的に減らすことを目指したデザインで、形状や色合い、質感を統一することで、極力存在感を抑え、建築自体の美しさを阻害しないこと、統一感のある空間づくりに応えている。また、製品の小型化や部品点数削減などによる使用材料の低減、梱包や取扱説明書の資源削減など、多角的な視点から環境に配慮した取り組みも重ねている
――野崎さんも、パナソニック製品の変化を感じますか?
野崎Make New Magazineの記事でも紹介されていましたが、2023年のグッドデザイン賞で金賞を受賞した電気シェーバー「ラムダッシュ パームイン」には驚かされました。シェーバーではあたりまえの機構である持ち手をなくし、代わりに「人の手」をシェーバーのUIに組み込んでいる。本来、機械よりも細やかな感受性を持つはずの手の感覚を、もう一度信じよう。そんなメッセージが込められているような気がしました。
同年のグッドデザイン賞ではパームイン以外にも、さまざまなパナソニックの家電、電設資材、建築材などが受賞していましたが、そのすべてに共通して「人とモノの関係性を見つめ直す」という意志を感じたんです。単純に見た目を綺麗にかっこよく整えるという前時代的な考え方ではなく、もう一歩踏み込んだデザインに取り組んでいるのかなと。

負い目をあえて隠さない勇気が必要
――ほかにも「Make New Magazine」で気になった記事はありますか?
野崎『棄てていた家電がよみがえる。再生済中古品事業が、3年の苦闘を経てビジネスになるまで』という記事も気になりました。
家電の初期不良品を再生し、品質保証をしたうえで「検査済み再生品」として再販売するという内容でしたが、スマイルズも「PASS THE BATON」という現代のセレクトリサイクルショップを展開し、リサイクルの新しい潮流をつくろうとしてきたので、パナソニックがこれまでにない中古品販売事業を始めたというのは興味深いです。メーカーとしては難しい判断もあったと思いますが、数年がかりで課題を乗り越え、事業を軌道に乗せていったストーリーにも刺激を受けました。
高品質でありながら新品よりも安価ということで、20代〜30代の若い人たちから注目を集めているというのもいいですよね。パナソニックを知らない若者も増えてきたなかで、若い人がパナソニック製品を手にする、最初の敷居を下げるという点でも意義のある取り組みだと思います。
――永山さんはいかがですか?
永山私も再生済中古品事業の記事を興味深く拝読しました。本来、初期不良品などはマイナスのイメージがあり、メーカーとしては表に出したくないところだと思います。でも、それを隠さず、むしろマイナスをプラスに変えていこうというパナソニックの思想が感じられました。
今は世の中的にも、これまで隠されていたものに光を当てていこうという流れになっていますし、そうした企業や製品が評価される時代になりつつある。この良い流れを止めないためにも、パナソニックが先頭に立ってどんどんやってほしいと思います。

本記事では、PFR事業化を推進した宮瀬健一(みやせ・けんいち)に、着想から本格的な事業化までの約3年にわたる試行錯誤や苦労、好調要因の「2つの大きな背景」、PFRの今後について、掘り下げている
わたしたちがパナソニックに期待すること
――最後に、未来に向けてパナソニックが果たすべき役割や、お二人がパナソニックに期待することを教えてください。
永山今回、万博のパビリオンを手がけるなかで、未来について考える機会が増えました。そこで気づいたのは、一気に何かを大きく変えようとすることが、必ずしも良い結果にはつながらないということ。リサイクルの話もそうですが、これまでできていなかった「あたりまえ」に目を向けて一つひとつ解決していくことが、ポジティブな社会をつくっていく。そういうシンプルな話なのかなと。
未来はいきなり訪れるわけではなく、「今」と地続きです。先ばかりを見ず、今の世の中を見渡す。ときには過去を振り返って参照することも大事です。パナソニックにはそうやって、足元にあるあたりまえを大切にしながら良い未来をつくってほしいと思います。
野崎そのあたりまえって、外から見れば「今さらそんなことをやっているの?」「そんなの意味ないでしょ」「ビジネスになるの?」と言われてしまうようなこともたくさんあると思います。もしかしたらMake New Magazineで紹介されている取り組みの多くが、今は無駄なアクションに感じられるかもしれない。でも、そうした取り組みのなかから得た気づきが、人々の生活を変える源になってきたことも事実であって。パナソニックに期待するのは、まさにそこですね。
どんなに懐疑的な目を向けられても気にせず、関西の企業ならではの遊び心を発揮しながら突っ走ってほしい。そして、最終的には世の中の「Make New」を生み出す、その決定打を打ち込むような存在であってほしいと思います。
Profile

野崎 亙(のざき・わたる)
株式会社スマイルズ代表CCO。全ての事業のブランディングやクリエイティブの統括に加え、入場料のある本屋「文喫」や東京ミッドタウン八重洲内の「ヤエスパブリック」など外部案件のコンサルティング、プロデュースを手がける。

永山 祐子(ながやま・ゆうこ)
2002年永山祐子建築設計設立。「ルイ・ヴィトン 京都大丸店」「ドバイ国際博覧会 日本館」ほか。『大阪・関西万博』では、パナソニックグループパビリオン「ノモの国」とウーマンズパビリオンを手掛ける。